


教授 [e-Mail] toshima
岡山県の岡山白陵高校の出身です。京都大学農学部の大学院を卒業して水産大学校に赴任しました。京大では海洋細菌の研究をしていました。今は、どのよう にすれば魚の美味しさを保てるのか、安全性が確保できるのかについて、魚の殺し方・冷やし方・保存方法について研究しています。最近では−25℃のアル コールで凍結したマアジが刺身で美味しく食べられることがわかりました。鮮度の高い魚を急速に凍結することがポイントです。
古下 学[博士(医学)]
准教授 [e-Mail] furushita
准教授 [e-Mail] watsuko
沖合底引き網漁業では種々雑多な魚類が混獲され、単一の魚種としては少量で種類も多く、市場に出しても安価で取引されています。そこでこれらの魚に付加 価値をつけ、有効に利用するためにはどのような加工が向いているのかを研究しています。また、魚臭のマスキング効果があると言われているゴボウのマスキン グ効果を調べる実験や、冷凍魚の冷凍保管温度と貯蔵期間が魚肉の品質に与える影響についての実験もしています。

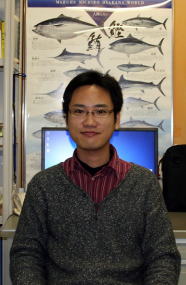
准教授 [e-Mail] tsubasa
岡山県の岡山大安寺高校出身です。大学時代には、主にカビを利用したバイオコン バージョン・バイオレメディエーションに関する研究に従事してきました。現在は、芝教授と古下講師とともに魚肉を腐敗させる細菌の動態に関する研究を行っ ています。さらに、これらの細菌による魚肉汚染を消費者が簡易に判断出来るセンサーの開発にも従事しております。また、学生時代の研究を活かし、日本の伝 統文化であるカビを利用した麹による新たな水産発酵食品の創生にも取り組んでいます。
助教[e-mail] yaguchi
静岡県浜松市出身。浜松西校の理数科を卒業して、山口大学農学部に入学した後は、主にネギやタマネギ、ニンニクといったネギ属野菜の機能性成分の増強を 目指した成分育種法の開発・研究をしてきました。様々な縁があって、平成25年4月に水産食品の分野へ飛び込んできました。野菜はもちろんですが、魚介類 もおいしいですね。おいしい水産物の鮮度保持や保蔵のための研究技術開発等に取り組んでいきます。
辰野 竜平[博士(水産学)]
講師 [e-Mail] tatsuno
佐賀県唐津市の唐津東高校出身です。海が近いのどかな町で育ったことから海洋生物に興味を持つようになり、長崎大学水産学部へ入学しました。同大学では博士号取得まで一貫してフグ毒保有魚類におけるフグ毒の体内動態とその分子メカニズムの研究に明け暮れました。その後、数年間の研究員の職を経て、水産大学校へ着任いたしました。現在、所属する研究室では古下准教授、福田助教とともに微生物を主体とした研究を展開しています。今後も「水産食品の安全利用」に貢献できるように研究を推進していきたいと考えています。
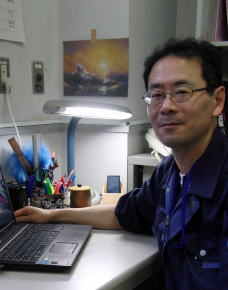
講師 [e-Mail] ookubo
福岡県北九州市「小倉生まれで響灘育ち」です。子供の頃に北里柴三郎先生の伝記に感動して研究の道を志しました。長崎大学水産学部で生涯の恩師と出逢い「科学と真摯に向き合う精神」を学び、かまぼこの「火戻り」の原因物質(酵素)の単離に成功して博士号を取得しました。その後、中央水産研究所では多回産卵魚(マミチョグ)でLHサージの存在を解明し、当時の先生から「多様な海洋生物の生命のロマン」を教わりました。夢は、酵素の単離に留まらず、北里先生のようにその実用化までを、水産分野で達成することです。本校では、これまでの経験を総動員して水産食品分野の様々な問題に取り組みながら、若い皆さんに先達から学んだことを伝え継いでゆけたらと願っています。



教授 [e-Mail] taiko
京都生まれの神戸育ちで、兵庫県立兵庫高等学校卒業です。京都大学農学部から同大学院の博士後期課程を経て本校に赴任しました。学生時代は、安定型ビタ ミンCの魚での代謝・生理活性の研究をしていました。本校では水産動物が好む味とにおい物質の研究を15年以上続けてきました。 その後、対象を魚から人間へ シフトし、鮮魚や水産加工品のフレーバー改善などの水産食品のにおいに関する研究を行っています。
近年はフグの美味しさ、北九州の郷土料理の魚の“ぬか炊き”や山口県との共同研究で酒粕入り飼料を与えて魚の香味を改善する研究などを行っています。
教授 [e-Mail] mic
(研究科併任)
有機化学,物理化学などを担当しています。大学を卒業してから水産庁水産研究所に採用になり,今年,水大校に異動してきました。酵素やペプチド,微量成分の精製やバイオアッセイが得意です。化学と食品製造を通して,専門家の養成に貢献できればと思います。
クロマグロ血液のセレノネインはヘム鉄の自動酸化を抑制することから,魚やヒトが酸欠状態で潜ったり,ストレスに耐えるのに必須な分子であると考えられ,未知の食品機能を解明します。
海洋で生物濃縮された水銀やヒ素などは,食事から摂取することは避けられません。これらの生物影響を分析し,食の安全確保に貢献します。こうして,水産物の美味しさに関する根拠を明らかにします。
研究紹介 セラミド セレノネイン
教授 [e-Mail] mmiyata
出 身地は広島で、東京、仙台を経て下関の水産大学校に赴任しました。理学部出身で、これまで企業と大学の医学部、薬学部に在籍した経験を持ちます。会社では 安全性評価等で医薬品の開発に従事しました。その後大学では薬物代謝酵素の機能と発現調節の研究や米国留学中に作製した脂質代謝異常や糖尿病などの病態モ デルと考えられている胆汁酸受容体欠損マウスを用いて脂質代謝調節についての研究を実施してきました。水産大学校ではこれらの病態モデルを用い、水産資源 中に含まれる機能性成分について研究し、水産資源の食品への応用に役立つ研究を実施していきたいと考えています。
研究紹介


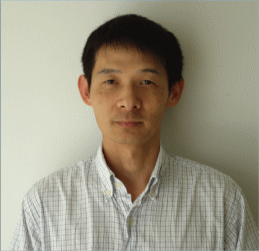
教授 [e-Mail] ikehara
(研究科併任)
沖縄県出身で、琉球大学理学部生物学科を卒業。琉球大学理学研究科及び、同医学研究科で学び、学位(医学博士)取得後は、埼玉県、長崎県などで研究生活を 送ってきました。これまでに、「食品や環境中の有毒成分の分析法開発」や「生物資源の有効利用」を目的とした応用研究を行い、下痢性貝毒やシガテラ等の魚 毒について、その検出法に関する技術開発や開発した技術を利用した製品開発等を行ってきました。水産大学校では、食品を含めた水産生物資源の機能解析を行 い、水産業振興に貢献できる情報を発信していきたいと考えています。
准教授 [e-Mail] usuim
山口県立萩高等学校を卒業後,山口大学農学部での学部・修士・博士課程を経て下関の本校に赴任しました。生れも育ちも学校も仕事もすべて山口県です。学 生時代は歯周病原性細菌の口腔内付着機構や卵・大豆・スギ花粉アレルゲンのアレルギーリスク低減化に関する研究をしていました。現在は,エビ・カニアレル ギーの原因タンパク質について「耐熱化機構の解明」「胃潰瘍とアレルギー発症リスクの関係解明」「リスク低減化や治療薬への応用」などをテーマに研究して います。美味しいエビを安全に食べ続けるため,エビアレルギーの人が危険回避するための「科学的根拠に基づいた正しい方法づくり」に取り組んでいます。
杉浦 義正[博士(学術)]
准教授 [e-Mail] ysugiura
学生時代は牛乳成分の機能性研究をテーマとして取り組み、大学院修士課程を卒業して食品メーカーに就職しました。そこで海藻成分の機能性研究をすることになり、研究素材が山(牛乳)から海(海藻)へと大転身しました。
これまでに、海藻成分(特に海藻ポリフェノールであるフロロタンニン)の抗アレルギー性について研究してきまして、そのご縁あって博士号を取得し、水産
大学校に赴任しました。今後は、研究活動を通じて、抗アレルギー効果に限らず、健康に良い事など海藻の素晴らしさを社会一般に広めていきたいと考えていま
す。
研究紹介

講師 [e-Mail] kawabe
出身は大阪府です。大阪府立三島高等学校を卒業後、福井県立大学の海洋生物資源学科に入学し、学位取得まで福井県小浜市で暮らしていました。学生時代は食品化学研究室に所属し、活マガキの水揚げ後に変動するエキス成分の分析や転写因子の解析を行ってきました。学位取得後は福井大学医学部で生殖内分泌学および癌の研究に従事しました。医学部で6年間研究生活を送った後、平成28年4月から水産分野に戻ってきました。水産大学校では、美味しいお魚を一人でも多くの人に食べてもらえるように、宮崎教授とともに水産食品のにおいの改善に関する研究に取り組んでいます。
研究紹介