2008年8月4日
先日に続いての第2弾。「水産食品士」について芝食品科学科長に聞きました。
----------水産食品士は大学独自の資格だと聞いていますが、どうして創設することになったのですか?
5年以上も前になると思いますが、理事長による『水産大学校独自の資格について検討しろ』と言った発言が最初です。当初は、「世間で評価されない資格など創っても仕方ない」と思ったものです。それでも理事長の発言ですから、どうしたら良いか考えていたのですが、答えが出ないままに時が過ぎていきました。

校門付近からの風景;左手の上階が突き出たのが食品科学科
----------それがどうして発足に漕ぎ着けることが出来たのでしょうか?
一般に大学独自の資格を創設するのは、学生の就職を有利に運び、学生の募集に繋げるためです。しかし、水産食品士は全く別の理由が切っ掛けとなりました。つまり就職状況が昨今の社会情勢で上向いたのが切っ掛けとなりました。学生の就職先に水産分野とは関係ない会社が増えてきたのです。菓子製造会社はその典型です。
-----------別にお菓子屋さんでも構わないのではありませんか?
いえ問題です。第一に、菓子製造会社ですと水産大学校で学んだ内容を活かすチャンスが減ります。その結果、社内での同僚との競争に勝つチャンスが減ります。私は、現在のビジネス環境では重役になれなければ、定年は全うできないと推測しています。競争に生き残る必要があります。
第二の理由が納税者に対する責任です。卒業生が水産分野に就職しなくなれば、水産大学校である必要はなくなってしまいます。
----------つまり、水産分野への就職を促進するために資格を創設したのですか?
そうです。水産分野に就職して欲しいのですが、強制することは出来ません。学生の自由意志で就職して欲しいのです。そうなるには、水産分野に対する興味を高めてもらうしかありません。
----------水産食品士の資格創設には、先生自身が調理を始めたことも切っ掛けとなったと聞いていますが?
え!そんな事も知っているのですか?参ったな!

正面が調理実習を行う食品加工実習工場
----------資格の名称を水産食品士とした理由は?
当初は、お魚コンシェルジェを用意していたのです。お魚の道案内人と言う意味です。ところが、高校生や食品科学科生にアンケートをとってみると、圧倒的に水産食品専門士が票を集めたのです。お魚コンシェルジェは惨めなほどでした。それで水産食品専門士に決め、商標登録の準備をしていたところ、専門士は、文部科学省が専門学校修了生の称号として使うことを決めていました。それで、縮めて水産食品士としました。
----------水産食品士に対する学生の評価はどうですか?
意外にも高い。特に卒業生からの評価が高い。『自分の在学中にこんな教育内容があれば良かったのに』と言う反応です。なんでも、『水産大学校を卒業したのだから、魚くらい捌けるのだろ』と言われて困ったとか。また就職した途端、消費者の食品の選択基準、つまり味覚の部分について相当なアンテナをはらなければならないようです。こんなことは、直ぐに出来る訳ではありません。
----------今後の展望を聞かせてください。
水産食品士の創設で、食と食品、科学と文化が融合することを願っています。
----------言葉が逆転しましたね。
ええ、食と食品、文化と科学の融合とも言えますが、わたしどもの基盤は科学です。科学と文化と言わなければなりません。
----------食と食品はこれまで融合していなかったのですか?
正確に言えば、科学が細分化するなかで強く意識されなくなった。融合とは、この場合強く意識することです。
----------食と食品の融合は、水産食品士で完結するのですか?
水産食品士の資格には調理実習と学科必修科目のほかに、学科14選択科目のうち11科目の履修が必要です。つまり食品全般の知識が必要で、さらに必修科目の栄養生理学で食品の消化吸収システムや、微生物学の授業では感染症を導入部分にして、免疫寛容と食品アレルギーの関係について教えています。つまり、「食べるとどうなるか」の科学的側面を教えています。また質問にはありませんが、文化については、出来るだけ外部の識者を招聘して学生の指導にあたると同時に、その過程で教員自身が食文化についての知識を深めていき、学生指導にあたることが出来るようにしたいと考えています。
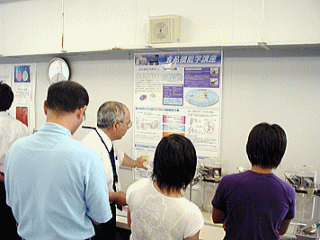
食べたらどうなるか?食品機能学講座の説明
----------最後に、企業による水産食品士の評価はどうですか?
うけは良い。非常に良い。まさに『こんな教育をやって欲しかった』と言う感じです。つまり資格そのものよりも、資格によりうらづけされた教育内容に対する評価です。
---------どうも先生は自画自賛が多いようですね。
すいません。根が単純なものですから、お世辞でも真に受けがちです。それでも色々な数字を見ても、良い結果が出ています。答えになりませんが、先日行った私の食品衛生学の試験結果でも、優に達した学生が3割になりました。例年数名しかいなかったことと比べると、大変な出来事です。
---------有り難うございました。水産食品士、頑張ってください。
有り難うございます。
その1の記事へーー>
