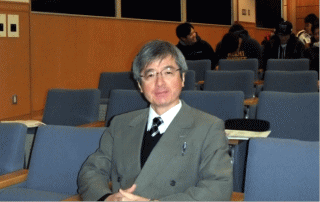
花岡研一先生
Q: 学生に対して、『出席してくれて有難う』なんて、花岡先生らしいですね。
A: 昨年、退職された松下先生からの電報は、心暖まるものだったね。
Q: 花岡先生は、32年間ヒ素の研究一筋。最後の10年間は厚生労働省の委託研究や食品安全委員会の委員で、随分と忙しくされたんですね。
A: もう11年になるかな、イギリスから「海藻にヒ素が沢山含まれている」って話が飛び込んできたのは。あせちゃってね。
Q: 誰がですか?
A: 勿論、花岡先生だよ。断片的な知識だけがクローズアップされれば、ヒジキの安全性が懸念されてしまう。日本人が昔から食べてきたんだから、問題ある訳ないんだ。
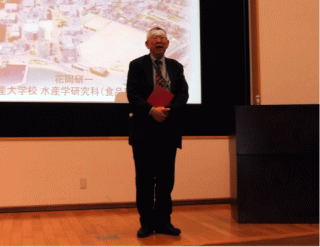
原田学科長の挨拶
手元には松下先生の祝電
A: いや、その前からだね。ヒ素で学会賞ももらっているし、何しろ、ヒ素と言うと、花岡先生の名前が直ぐに出てくるくらいだから、厚生労働省の委託研究を続けていたんだ。
Q: 講演では、「水産物には無害の有機ヒ素化合物として集積しており、たまたまヒジキには無機ヒ素が多く含まれているけど、水晒しすれば、殆どが溶出してしまう」ってことでしたね。
A: そうなんだよ。伝統的な食べ方が、如何に優れているかの見本だね。
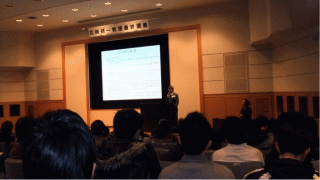
花岡先生講演風景
A: 『何時だったか」じゃ、困るんだよなあ。ちゃんと覚えておいてくれないと。タケノコには青酸配糖体が多く含まれているんだけど、煮込むと危険性がなくなる。「湯を沸かしてから掘れ」は、昔からの教えだね。
Q: 会場の理事長も挨拶で強調されてましたね、伝統的な食べ方の大事さを。
A: そう。先人の知恵には、一万年の厚みがあるからね。
Q: 先生も大袈裟ですね。
A: 大袈裟じゃないよ。君も、もう少し素直でないとなあ。

鷲尾理事長挨拶
A: 分野外だと言われていたけど、必要にかられてね。臼井先生らとマウスを使った実験を行ったんだ。
Q: 分野外と言えば、東北大震災の直後には、食品の放射能汚染の問題を審議する委員も花岡先生はされてたんですね。
A: あのころは、殆ど毎週のように食品安全委員会に出席していたんじゃないかしら。
Q: それで、食品の放射能レベルについての新たな基準が出来たんだから、花岡先生も本望だったんじゃないでしょうか。

花束贈呈(研究室の学生から)
Q: 僕も将来そんな成果をあげてみたいな。
A: ま、頑張ってね。