A: 論文の提出期限が2月21日。みんな真っ青だね。
Q: 4月からだと約10ヶ月。就職が決まったころからでも7ヶ月になりますね。
A: 就職は、友達が決まってるのに決まらないと焦るよね。
Q: 研究室の様子って、みんな知りたがってるんじゃないですか。
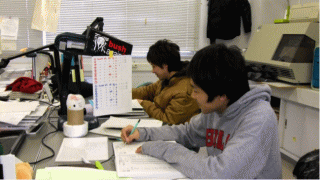
みんなで励むデスクワーク
Q: 計画的ですか!?
A: 何時計画を練り、まとめを行うか、決めておかないとね。四六時中試験管をふっていれば、記録が残らない。また勉強する時間も必要なはずだ。
Q: ノートでは、皆ヒーヒー言ってましたよ。奇麗にって、言われて。
A: ノートって、脳みその一部なんだね。ノートがゴチャゴチャなら、それを読む人の頭もゴチャゴチャ。奇麗でなければ、結果をみても良いヒラメキは生まれない。
Q: それは色んな事に通じそうですね。
A: 卒研って、研究を体験させることばかりではないんだ。社会で働くうえでの基本的なノウハウを教えることも狙ってる。
Q: 朝のミーテイングで、「昨日は何をやった。今日は何をやる」の報告もそうなんですか。
A: そう。人は一日の始まりの時点で、その日の過ごし方が自覚されていないといけない。
Q: 今年の研究室の卒業研究はどうでしたか?
A: 色々だね。抗生物質耐性菌では新しい耐性遺伝子が見つかったし、オキアミを使った味噌もできた。
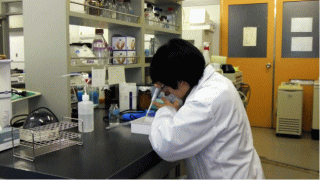
遺伝子の探索風景
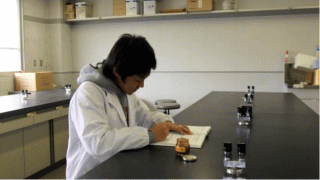
オキアミ味噌の検査
A: それが結構美味しいんだよ。麹の力だね。酵素活性を測定したかと思えば、舐めて成果を確認したり。楽しかったんじゃないかな。
Q: 細菌センサーは?
A: 冷蔵中の刺身の細菌汚染レベルが基準値を超えたら、小さな布切れのセンサーが変色するって奴なんだけど、今年はセンサーの感度をあげる研究に終始したようだ。

細菌検査の光景
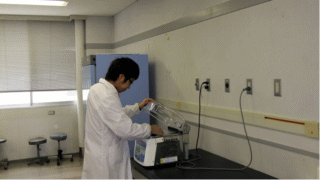
超高圧用試料の準備風景
A: 毎週、実験が終わるたびに、学生と教員でデイスカッション。わくわくするような毎日だったね。
Q: 学生がアイデアを出すときもあるんですか?
A: 10分の1くらいかな?むしろ、観察結果についての質問攻めに合う事が多い。
Q: それって、大事だし、大変じゃないんですか?
A: そうなんだよ。観察って、言われた事だけをやっていれば良い訳じゃない。実験をしている時に、みずからが大事だなと判断することを記憶し、記録することなんだ。
Q: 観察力は社会にでて役立ちそうですね。
A: それが狙いだからね。