A: オトソあけで、皆少しぼうっとしているんじゃないかな。
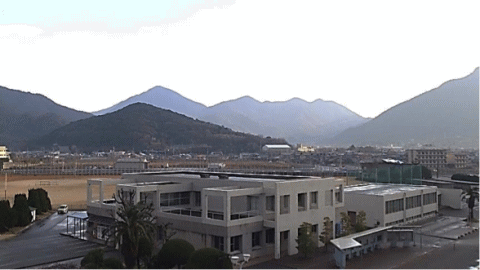
コミュニテイホールと鬼ケ城(山)
A: 前半が終わったところなんで、義務表示と不当表示の問題を出したんだ。ま、みんな結構書けてたんじゃないかな。
Q: そもそも食品表示の講義なんて珍しいですよね。
A: 水産大学校くらいかな?今年で2年目だ。
Q: 先生は、もともと微生物の専門なんで大変じゃないですか?
A: 最初の試みが学生さんとの自主ゼミで、2006年に始めたんだ。みんな熱心でね、当時の学生は卒業後、直ぐに表示の総責任者になったくらいだ。
Q: で今は?
A: みんな苦労しているね。そもそも大変難解な規則だから。例えば「おいしい」が不当表示かなんて、理屈で考えても分からない。結局、判例をたどるしかないんだね。

奥左が講義棟
A: 内容が煩雑なんで、理解してもらうために、できるだけ規制が導入された原因や理由を説明するようにしている。
Q: 例えばどんなですか?
A: 食品添加物には物質名と併せて用途名を表示するものがあるんだけど、リストを見ると食の安全に関心の高い消費者が一番敏感な品目が並んでいるんだ。
Q: どこからそんな情報を仕入れるんですか?
A: 消費者庁、厚生労働省、農林水産省だね。
Q: そこにも情報が無い時はどうするんですか?
A: 判例なりの根拠を引用して解説している、企業や企業組合の「お客様用の」ホームページを参考にする。
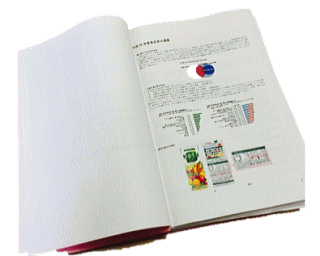
食品表示のテキスト