世界では未だ8億人もの人が飢餓に苦しんでいるそうです。(文献1)また最近では将来の食糧不足が騒がれ始めました。この危機に対処しうるのが養殖漁業です。この養殖漁業の発展で問題なのが、魚の病気と安全。コースはこのために必要な知識・技術を教えます。
食糧不足の実態はどんなものですか。
答えるのが難しいですね。世界の人口が現在の66億から2050年には90億になると言われています。(文献2)果たして足りるのか?もうひとつは、中国とインドが発展し始めて、先進国の消費人口が少なくとも10億人から約40億人以上になる。やはり果たして足りるのか?正確な答えに窮します。
食糧不足だとしたら食糧を増産しなければいけませんね。
ええ養殖漁業は1980年代から急激に発展し、数百万トンでしかなかった生産量が2005年には4,800万トンにまで増え、食用水産物の半分近くに達しています。これからも増やすことが出来ます。(文献3)
どこでそんなに増えているのですか。
まず中国です。2005年に約3,200万トンに達しています。そしてインド、インドネシアと続きます。インドネシアの伸びは大きいようで、1980年初頭には30万トンを超える程度だったのが2007年には308万トンにまで増えています。恐らく現在は中国の次ではないでしょうか。研修生のへシーさんによれば、エビ養殖が盛んだそうです。(文献3、4)また最近10年間では、実に様々な国で驚異的な伸びとなっています。
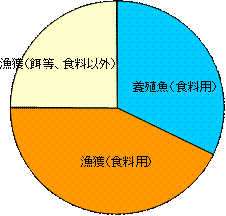
高級品を輸出して外貨を稼ぐためと、国内の重要なタンパク資源として利用する場合があります。前者はエビ養殖やサケなどが主で、後者にテイラピアやコイなどがあります。前者にはインドネシアなどの国、後者にはアフリカなどの国々があります。(文献3)将来どちらの方向に進むのかと研修生に聞いたところ、全員からBothだと言う答えがありました。
研修生の出身国はどんなですか。
ケニア、トルコ、インドネシア、カンボジア、マダガスカル、ブルネイ、ラオスです。
ラオスとは珍しいですね。
海がありませんからね。ただラオスは養殖が盛んで、生産量が採る漁業の3倍近くに達しています。養殖漁業が採る漁業を上回る唯一の国でしょう。ラオスの養殖漁業は1995年から急激に発展しました。やはりテイラピアやコイが主要な養殖魚です。(文献6)
国をあげての殖産なのでしょうか。
そうです。ただ下地の無いところでの急激な発展は無理なので、伝統的、つまり小規模の漁をする人が多かったのかと研修生のアカネさんに聞いたのですが、違うとのことです。普段の生活に魚採りが密着しているのだそうです。つまり夕餉のおかずを採る感じです。
するとラオスこそ研修コースに相応しいと言えますね。
ええ、そうなのですが、ラオスにはまだこれと言った病気の被害が無いようです。人口密度が低いので、粗放的な養殖なのかも知れません。
だとしたらラオスにはどんな協力が有効なのでしょうか。
品質管理技術と養殖技術全般ではないでしょうか。養殖技術ではFAOによる協力が大きいようです。またラオスでは日本の漁業法に相当するFisheries Lawを準備中のようですが、これもFAOの協力のもとで作業しているようです。

漁業法であれば日本こそが協力すべきではないでしょうか。
ええ、アカネさんはFisheries Lawの立法作業班に入っているそうです。今日も日本の漁業法を紹介したのですが、果たしてどうでしょうか。日本は漁業の歴史がながく、それにともなって漁村も発達していました。それに比べラオスには漁村のようなものは無かったようです。
聞きたい質問はまだありますが、10月末までの研修だと聞いています。また聞かせてください。
解りました。宜しくお願いします。
文献1;The spectrum of malnutrition" (pdf). Food and Agricultural Organization (2001-10-05).
文献2; World Population Prospects: The 2006 Revision, United Nations Department of Economic and Social Affairs
文献3; State of World Aquaculture 2006. FAO
文献4; Country Report on Indonesia in the Training Course for the Prevention of Cultured Fish Disease and Fish Borne Disease, Hamdani Novita Hessy, (2008)
文献5;Nearly half of all fish eaten today farmed, not caught. George Kourous, Information Officer, FAO (2006)
文献6; Fishery and Aquaculture Country Profile, Lao People's Democratic Republic FAO (2006)