まあまあ、そう焦らずに。インタビュアーの君は、以前、生協でフグの魚醤の「ふく醤油」を販売していたのは知っていますよね。
ええ、知っています。そう言えば、生協の棚から、いつの間にか姿を消して随分たちますねえ。
そうなんです、第一期の仕込み分が完売して、売り切れていたのです。でも、お待たせしました。第二期分の製品が完成し、まもなく、生協の棚に再びフグの魚醤が並びます。
そうだったんですか。でも、その話が「くじら醤油」の新発売と、どう結び付くのですか?
まあまあ焦らずに。今回発売する第二期のフグの魚醤は、以前と異なり、新たにヤマカ醤油株式会社さんが製品化してくれたんですよ。ですから、名称も「ふく醤油」から、「ふく魚醤」に変わり、パッケージもラベルも一新しました。
ああ、国道191号線沿いに面して、安岡にある大きな煙突が目印の、建物の壁に大きく「ヤマカ醤油」と書いてある、あの会社の事ですね。
ほお、君もちゃんと知っているのですね。そのヤマカ醤油さんと「ふく魚醤」を製品化する際に、併せて、「くじら醤油」も「うに魚醤」も共同で開発したんですよ。
でも、鯨で醤油作りとは驚きました。その発想の原点はどこにあるのですか?
調査捕鯨で獲られた鯨はもともと、棄てる所がないと言われる程、有効利用されていますが、それでも赤肉を鋸で引いて分割する時に、鋸屑肉が発生していて、その赤肉の屑肉は廃棄されていたのです。それを利用しない手はないと思い、醤油を作ろうと思ったのです。

ヤマカ醤油(株)の工場にて、「くじら醤油」の商品化に向けて0.5トンの大量醸造開始
(2008.12.10撮影)
ご心配の通りです。鯨で醤油を作ると記者発表したその日の晩から、ネット上で、賛否両論の大騒ぎとなりました。でも、棄てる肉を有効利用するという観点でしたので、概ね、好意的な意見が半数を越えていた様な気がします。
それから、君は、今、無造作に「鯨で魚醤」と言いましたが、実は、その発言には大事な内容が含まれています。良く考えて下さい。鯨は魚類ではなくて、哺乳類ですよね。ですから、「魚醤」という言い方は当たりません。恥ずかしながら、正直言いますと、僕も、最初は魚醤と言っていたのですが、共同研究者で「食の冒険家」として名高い小泉武夫博士にお会いした時に、「原田先生! 鯨は魚醤でなくて肉醤(にくびしお)に括らないといけませんね」と、指摘を受けました。「確か、日本の食文化の歴史の中で、肉醤の文化は、既に滅び去っていると理解していましたが、水産大学校の食品科学科は、失われた日本の食文化を、新しい形で復活させようとしている事になりますね。これはすごい事ですよ」と、こちらが恐縮する程、評価して頂いたんです。

「くじら醤油」を使った料理の一例の「鯨のベーコン」と「鯨の昆布巻き」
(山口県長門市にあるホテル楊貴館の取締役総料理長の山口弘幸氏の作品)
わかりました。実は、小学館という出版社から、東京の新宿高島屋というデパートで、「大学は美味しい!!フェア」に出品したらどうですか?と声を掛けて頂いたのがきっかけです。このイベント、全国の22国公立大学と6私立大学の合計28の大学が一堂に会し、それぞれの大学オリジナルの開発食品がいっせいに販売されます。水産大学校食品科学科の開発した「くじら醤油」、「ふく魚醤」、「うに魚醤」も、ヤマカ醤油さんが、水産大学校のブースで販売しますが、水産大学校側からは、私か和田律子先生が交代でブースに立ちます。そうですねえ、他大学では、例えば、山梨大学が「海洋酵母仕込みワイン」、近畿大学が「近大キャビア」、奈良女子大学が「奈良漬けアイス」、九州大学が「地どりソーセージ」、鹿児島大学が「篤姫酵母仕込焼酎」などなど、大学ならではのユニークな食品が並びます。
具体的には、6月11日(木)から6月16日(火)までの6日間、場所は新宿高島屋11階催し会場です。JR新宿駅の「新南口」改札口を出たら直ぐの場所です。販売の時間帯は、原則として、午前10時から午後8時までです。
うーん、相手は強豪揃いですねえ(笑)。先生、大丈夫ですか?
いえいえ、僕は、もっとポジティブな思考をしているのです。それは何かと言いますと、全国の数ある食品関係を持つ大学で、独自の開発食品を出せるのが、まだ全国に30大学しかないという事です。つまり、水産大学校食品科学科は、全国でベスト30に入っていると考える訳です。

新宿高島屋で新発売される「くじら醤油」と「ふく魚醤」の商品のイラスト図。
商品の背面のラベルには、水産大学校と共同で開発した旨、記載してある。
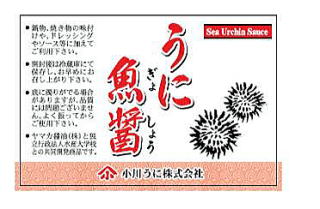
「うに魚醤」の瓶のラベル。水産大学校とヤマカ醤油(株)が共同で開発して、販売元は、下関の老舗「小川うに株式会社」
そうなんです。今回のフェアで小学館に協力している紀伊國屋書店新宿南店が、特別公開講座で講演会を行いますが、フェアの初日の更にトップを切って、私が「フグ、クジラ、ウニで作った魚醤油が持つ抗酸化能の観点から見た健康増進機能性」という演題で講演致します。
詳細は,「大学は美味しい!!フェア」と「特別公開講座」をそれぞれクリックしてみて下さい。
今日は、本当にお忙しいところ、どうも有難うございました。東京から戻って来られた時の土産話を楽しみにしています。
