今回は市民と高校生向けです。食品科学科の教育の新しい特徴を紹介します。つまり、
食品科学と食文化の融合
地域の人が参加する大学教育
そのために次のプログラムを用意しています。
時 : 10月13日(月曜日;祭日) 10:20〜15:30
場 所: 水産大学校講義棟
第一部 市民と学生向けの講演会 10:30〜12:30
1. 「ことばは味を超える」 大阪市立大学教授 瀬戸賢一
2. 「フグと下関」 直木賞作家 古川 薫
第二部 水産食品士のお披露目 13:00〜14:00
1. 「水産大学校生とフグ刺しをひいてみよう」(先着100名)
2. 「冷蔵庫で40日間寝かした無菌フグを食べてみよう」
第三部 食品科学科紹介 14:00〜15:30
1.教育・研究施設紹介
2.体験実験(出来るだけ事前申し込みしてください)
「DHA・EPA入りの機能性かまぼこの製造実験」
「海藻中のミネラル100種を5分で分析!」
「骨髄性白血病細胞を使って癌細胞を自殺に追い込んでみよう!」
ずいぶん盛りだくさんですね。まず第一部のねらいは?
瀬戸先生には、味表現について講演して頂きます。味をどうしたら正確に人に伝えられるか。微妙な味の違いをどう表現したら良いか。大事なのですが、大変難しい。
古川先生には下関とフグの歴史を話して頂けたらと思います。フグの美味しさには、色々な人が関与してきたはずです。つまり歴史のなかで美味しさが育った。こんなことが理解出来たらと期待しています。
第二部のお披露目はくだけた感じがしますね。
ええ実際にフグ刺しをつくって皆さんに楽しんでもらいます。
刺身をひくとありますが、切るのではなくひく。この”ひく”に巧みへのこだわりを感じます。巧みへのこだわりは集中力を高め、人を育てます。巧みへのこだわりのなかで育てた食品科学科の学生と腕を競ってみてください。
無菌フグは?
これはチョットずるいのですが、試食会をかねています。4℃で40日間保存した無菌フグと新鮮なフグではどちらが美味しいか。正確に言うと美味しさの違いを知ってもらいたいと思います。
第三部の主旨は?
主に高校生向けの内容です。水に油滴をたらしても混ざりません。機能性蒲鉾では肉と混ぜるのが難しいDHA・EHAを超高速ミキサーで混ぜるマジックを体験して頂きます。またミネラルの分析では、何千万円もする高額機器を使った実験の体験。癌細胞の実験では、癌細胞が1滴の食品成分で死んで行くのを顕微鏡下で観察してもらいます。
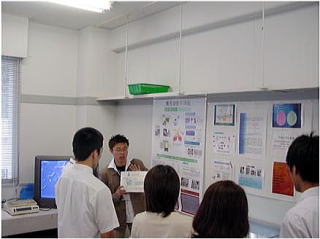

さてここからは趣旨を少し変えて、食品科学科の進もうとしている方向を、学科長の個人的意見も交えて教えください。
まず「地域の人が参加する大学教育」を説明してください。
水産食品士では、地元の料理専門家などに指導をお願いしています。例えば包丁の使い方を私たちは教えられません。授業科目の「魚餐とビジネス」や「魚餐と文化」では実務に長けた人や、食の歴史・文化に詳しい人の助けを借りています。これが「地域の人が参加する大学教育」です。
それですと地元のお世話になりっ放しですね。
ええ物事ギブアンドテイクであるべきで、当然地元への貢献を学科長として考えています。
産学連携ですか?
研究面での産学連携は、すでにかなり行っています。そうではなくて教育におけるギブアンドテイク、つまりサービス・ラーニングです。
と言うとどんな事ですか?
サービス・ラーニングは米国で盛んな大学教育の手法です。私の理解では大学で学んだことが実際の社会の問題解決に役立つかを、社会に出て検証する。つまりおしかけて行って、検証する。受け手からすれば迷惑な話ですので、お返しにサービスする。つまりボランテイア活動のなかで問題解決に貢献する。
ずいぶん難しい作業ですね。学生に出来ますか?
問題はそこです。「大学で学んだ知識を学生が地域に広める」ことをサービスだとする考えもあるようですが、不十分です。問題解決に参加させてもらうためにはまず役に立たなければいけない。知識だけで役立とうとすれば、いきなり学生が指導者の立場になる訳で、そんなことはありえない。
だとすればどうするのですか?
まずスキルをもって作業を分担させて頂く。つまり役にたつ技術をもって特定の仕事に参加するなかで、学んだ知識を検証し、控えめに意見を述べてみる。これであれば、仕事への参加で十分な貢献が出来ますし、意見が評価されれば目的を達したことになります。
どんなスキルを身につければ良いのですか?
英会話などがあるのでしょうが、食品科学科の学生はやはり食を作るなかで貢献すべきです。例えば地域の伝統的料理を学生が保存して広める。あるいは魚食の知識・技術を通じて貢献する。これであれば魚食にまつわる衛生や栄養の問題、さらには流通の問題に立ち会える訳で、知識の検証と提供が出来るのではないでしょうか。水産食品士にはそのようなことを期待しています。
随分遠大な話ですね。
私自身は、水産大学校の教員と学生が地域に自然に溶け込み、地域の貴重な財産になればと願っています。
どうも有り難うございました。
参考;http://www.servicelearning.org/